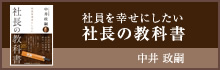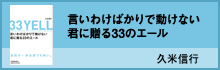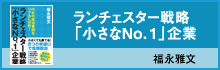-
組織のつくり方2014年7月
この新進気鋭トップの“勇気”に学べ! 挑戦する経営(株式会社システムインテグレータ・社長 梅田弘之氏)
 入念な準備が奏功し創業初年度から黒字化
入念な準備が奏功し創業初年度から黒字化
私が独立を考え始めたのは、東芝に勤めていた29歳ごろのことでした。それまでは定年まで勤め上げるつもりで、起業するなど考えもしなかった。一転して独立を考えるようになったのは、少し口幅ったい言い方ですが、自分の能力を発揮できる環境に身を置いて、思いきり働いてみたかったからです。社会経験や業務知識が増えるにつれて、自分自身を冷静に、客観的にとらえることができるようになったからでしょう。
私は、東芝の社員として働くうち、どうやら自分は新しいビジネスを企画したり、アイデアを商品化して勝負するような仕事が適しているらしい、と気づきました。自分の発想で様々に工夫を凝らして、世間を「あっ」と驚かす商品やサービスをつくってみたい、という気持ちが募(つの)っていくのを自覚するようになったのです。
当時、プラント系の技術者だった私の仕事は、規模の大きなプロジェクトを大勢の仲間と協力して推進するという性格のものでした。やりがいも大きく、仕事そのものは充実していたものの、私の希望を叶えるには、ふさわしいとはいえませんでした。
他部署への異動も考えましたが、東芝にかぎらず、大きな組織には特有の複雑な力学も働いていて、私の勝手気ままが許されるとは思えません。このとき、思いきって会社を飛び出してしまうのが、あるいは本当のベンチャースピリットかもしれませんが、私はリスクを回避しました。そのまま独立しても、私にはまだ武器といえるものが備わっていなかったからです。私は、装備を調えて、堂々と戦えるようになるまで、実力を養うべきだと判断しました。
雌伏(しふく)を心に決めた私は、タイムリミットを設定すべきだと考え、38歳を目安に独立しようと思いました。そして、具体的にどういう事業が最もふさわしいかを検討し、市場の将来性や自分の能力を考慮して、IT業界にねらいを定めました。その後、31歳のときに住商情報システムに転職して、IT業界での経験を積み、やがて当時の部下とともに独立することになります。当初の計画より1年早い創業でした。
初年度は、わずかな額ではあったものの、おかげさまで、黒字で終えることができました。翌年以降も、小さな黒字を積み重ねていきます。それは、おそらく独立を決めてから8年間も準備に努めてきたからでしょう。私の場合、そうしてじっくりと起業に備えた利点は、次の3点に収斂(しゅうれん)されると思います。
1つは、創業をすべて自己資金でまかなえたこと。当初から無借金経営が実現でき、ほぼ資金繰りに悩まされずに済みました。
2つめは、前職である程度の実績を残したこと。国内初のERPソフトを開発し、独立してもやっていけるという自信を得ただけでなく、業界内で少しは名前が売れたことも、のちに独立してから有利に働きました。
3つめは、それなりの人脈ができたことです。独立当初は、とにかく仕事をいただくために奔走せざるを得ないものです。その点、私どもも食い扶持の確保を第一に考えてはいたものの、培(つちか)った人脈のおかげで、仕事の依頼をいただく機会が少なくありませんでした。
ただ、そうして比較的、順調に成長してきた私どもにも、前述のように、いわば「反抗期」ともいえる試練が2回ありました。第一次反抗期は、2001年前後、ネットバブルが崩壊したことによる不況期で、第二次反抗期は2008年のリーマンショック時です。とくに、後者は深刻な危機でした。リーマンショックという外的要因に加え、知らず知らずのうちに社内に蔓延(まんえん)していた弛(ゆる)みが表面化して、これまでで唯一の赤字に陥ってしまったからです。
ネットバブルのころは、まだ創業から5、6年しか経っておらず、私自身、組織として未整備な面や従業員の実力不足を認識していました。業績が景気の動向に左右されても致し方なく、むしろ苦しい状況を奇貨(きか)として、従業員教育の充実や人材の補強に努めるきっかけにすることができました。
しかし、リーマンショックのときは、すでにマザーズへの上場も果たし、会社としてそれなりの実力を蓄えつつあるという手応えを感じていただけに、様々に露呈する脆(もろ)さが意外でもあり、私は危機感を強めました。
このとき目についた弛みとは、たとえば販売管理費率の高さです。ご承知のとおり、販売管理費率は会社のコスト体質を表わす指標で、本来、経営者として最も留意すべき数字の1つです。私も数字を把握していなかったわけではなく、その高さを懸念してはいました。でも、対策を講じてはいませんでした。「引き締めないといけない」とは言うものの、結果として高コスト体質を放置してしまったのです。
原因は、組織としての弛みにありました。創業から10数期しか経ていないにもかかわらず、習慣化した日常が油断を生み、徐々にコストが高くなっていく。それは一種の大企業病といってよく、私はこのとき、若く小さな組織にも大企業病が起こり得ることを学びました。
そして、そのこと以上に問題だったのは、私自身の弛みでした。端的にいってしまえば、高コスト体質を許してきたのは私の判断が甘かったからで、その甘さほど、当時の私の精神的な未熟さを表す事実はなかったでしょう。恥ずかしながら、そのころの私には従業員に嫌われたくないという情緒的な思惑があって、彼らから寄せられる提案を1つひとつ厳しく吟味するという姿勢に欠けていました。その蓄積が、結果としてコストを肥大化させてしまったのです。